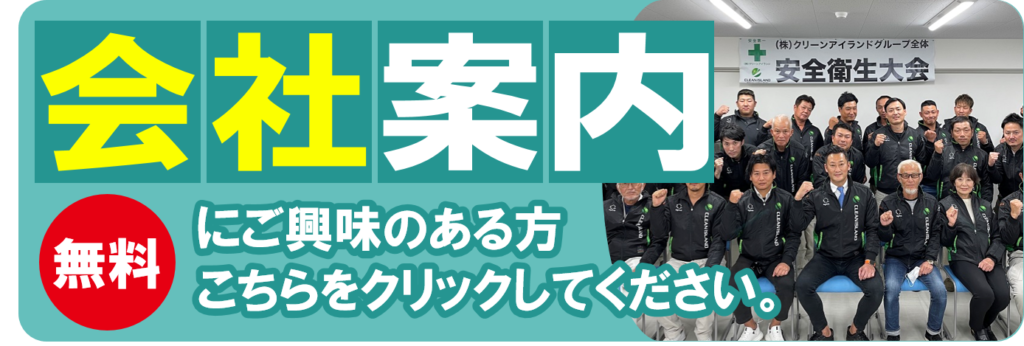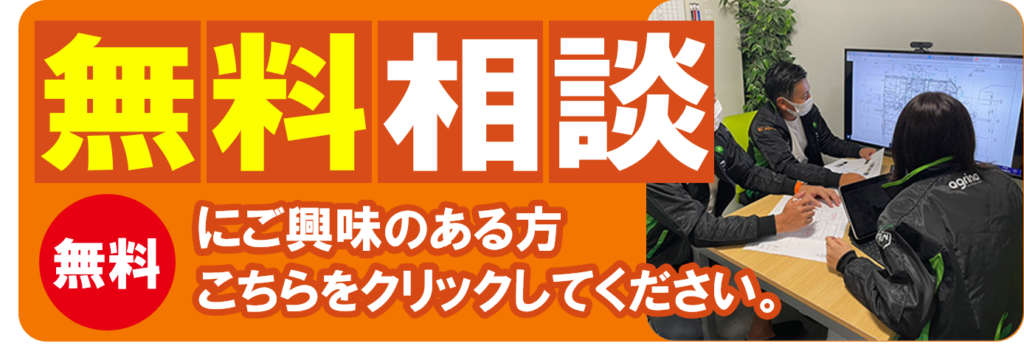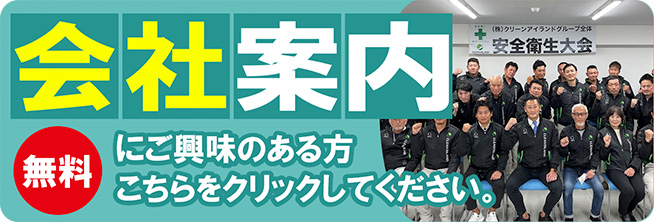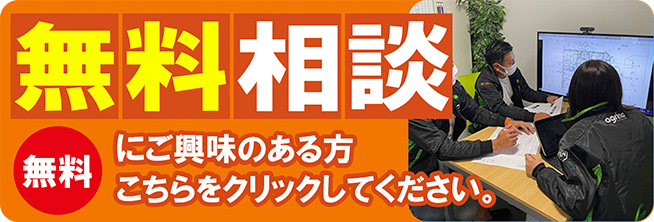新着情報NEWS
2022年10月24日更新 スタッフブログ
罹災証明書の申請方法について⑥
目次
罹災証明書の申請方法について⑥【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【罹災証明書の申請方法について⑥】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】罹災証明書の申請~発行までの流れ
- 【大阪 解体工事】市区町村・自治体の現地調査
- 【大阪 解体工事】発行までにかかる時間
- 【大阪 解体工事】自己判定方式について
- 【大阪 解体工事】まとめ
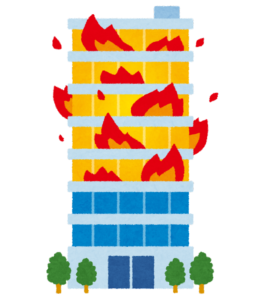
罹災証明書の申請~発行までの流れ
罹災証明書を実際に申請してからの流れはどうなるのかを説明します。
市区町村・自治体の現地調査
罹災証明書の発行申請を行うと、自治体の調査員による現地調査が行われます。
罹災証明書の発行申請が窓口に来た後、自治体は調査員を現地調査に向かわせます。
調査内容は政府が取り決めた内容に沿って基本的に行われます。大抵は目視によって、建物の損壊具合を認知し、次に建物の傾斜具合を測定します。
浸水など被害が内部にまで及んでいる場合は、被災者からの申請により内部調査も行います。
発行までにかかる時間
現地調査を終えた市区町村の担当職員は、内閣府の被害認定基準の運用指針に沿って被害の程度を判定します。
現地調査が終了した調査員はその結果を自治体に持ち帰り、職員が政府の被害認定基準の指針に従って被害状況を判定します。
この判定から罹災証明書の発行まで、現地調査を終えてから最低でも1週間はかかりますが、自治体事態も被害にあっているなど大規模な災害の場合はそれ以上伸びる場合もあります。
また、被災者は罹災証明書の判定結果に対し、満足がいかない場合は不服申立てを行うことが出来ます。
その結果再調査をしてもらえることもあるため、結界満足がいかない場合は不服を伝えましょう。
自己判定方式について
自治体によっては、自己判定方式(写真による判定)により罹災証明書を発行できることがあります。
このパターンは被害状況が軽く、住居人自身が準半壊のレベルに達していないという被害レベルに同意した時に行われるものです。
現地調査は行われず、申請者が短時間で罹災証明書を受け取ることができる長所を持ちます。
まとめ
今回は、【罹災証明書の申請方法について⑥】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。


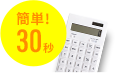 お見積依頼
お見積依頼

 MENU
MENU